

お電話でのお問い合わせ072-876-8700

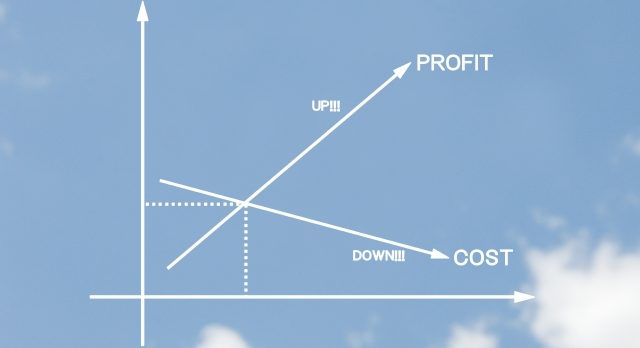
事業を行うためには資金調達が必要なのは金融機関も同じです。資金調達には直接金融と間接金融がありますが、ここではアクセスの容易さから間接金融を考えます。念のために、直接金融とは資本市場から直接資金調達を行うことを指し、代表例は株式公募や社債発行ですが最近ではクラウドファンディングもこれに該当します。これに対して間接金融は金融機関である商業銀行、信用金庫、信用組合、保険会社、農業協同組合、漁業協同組合等が資金の出し手となります。直接金融でも証券会社やクラウドファンディングのプラットフォームが資金の出し手ではないのかという疑問が出るかもしれませんが、彼らは資金の出し手ではなく仲介人にすぎません。間接金融機関である銀行等(文中以下「銀行」といいます)に焦点を絞るのは、間接金融機関からの資金調達と直接金融からの資金調達を比較した場合、一般的に銀行からの資金調達の方が容易だからです。ですが、創業融資に限って言えば必ずしもそうではないイメージがあります。これは銀行から資金調達を試みる場合は必ずと言っていいほど人的あるいは物的担保の何れかあるいは双方の担保が必要となるためで、創業社長の場合個人の連帯保証を求められ、ほとんどの場合生活の本拠となる自宅を物的担保に、自身を人的担保に供することになるからです。実は、平成26年2月から「経営者保証ガイドライン」によって一定の条件を満たせば経営者保証を外してもよいとなっていますし、さらに平成28年からは監督官庁である金融庁が「事業性評価」によって信用を供与せよといってもなかなか実現しにくいのはどうしてかを、最初に考えたいと思います。
銀行の任務は銀行法第1条で「この法律は、銀行の業務の公共性にかんがみ、信用を維持し、預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑を図るため、銀行の業務の健全かつ適切な運営を期し、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。」と規定されていますが、優先順序として①信用を維持すること、②預金者の保護をすること、③金融の円滑を図ることの優先順位を設けられています。また第2条で第2号第1項で「預金又は定期積金の受入れと資金の貸付け又は手形の割引とを併せ行うこと。」とあります。預金の受け入れが先に来ることからすると、信用の維持とを預金者の保護を金融の円滑化より先に来る、つまり貸出を優先するより預金者保護を優先させることを匂わせているかのような条文です。実際、現時点まではペイオフが実行されたことはありませんし、平成30事務年度まで銀行ににらみを利かせていた「金融検査マニュアル」が不良債権処理を優先させていたのは、戦後恒常的に余剰資金を持つ家計部門から資金不足であった企業部門に資金移動が行われていた構造が背景にあり、家計の資金運用は安全性を要求するという資金の出し手からのアプローチもできます。つまり、資金調達先である家計の特性を踏まえたうえで銀行への交渉を行う必要があるということです。
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。